── 理学療法士・山岸駿介さんの実例から
仕事を続けているけれど、「このままでいいのか」と、どこか迷っている人。
この記事では、理学療法士として働いてきた彼が、うまくいかなかった感覚や迷いを抱えたまま、仕事や自分自身と向き合い進んできた過程をお伝えする。
プロフィール

氏名:山岸 駿介
活動エリア:東京都内
肩書き:理学療法士
主な仕事・活動内容
理学療法士として、身体の痛みや不調に悩む人へのケアや運動指導を行っている。
医療・介護領域での臨床経験に加え、運動や予防の視点からのサポートにも関わっている。
これまでの経歴・経験
学生時代、勉強や実習において「才能がない」ことに悩む。新人時代、現場での経験を重ねる中で学びと結果が結びつく感覚を得る。
結婚・出産をきっかけに、働き方と家族との時間のバランスを見直す。現在は、仕事の軸を保ちながら、関わり方を模索している途中にある。
各種ページ・SNS
【Instagram】希望のココカラlabo
【Youtube】やま先生のひざ痛解決TV
ターニングポイントを「考えたことがなかった」
事前アンケートを振り返りながら、彼はこう話した。
「答えられるものはすっと書けたけど、ターニングポイントって、あんまり考えたことなかった」
人生の節目を意識的に整理することは、これまでほとんどなかったという。
ただ、話を進めていくと、学生時代の実習、新人として働き始めた頃、子どもが生まれたタイミングなど、いくつかの場面が自然と浮かび上がってきた。
学生時代、納得できないまま終われなかった
学生時代、彼はテニス部に所属。部内戦で四位に入り、レギュラーになれる成績を残した。
それでも、実際に試合に出るメンバーには選ばれず、五番手の選手が先に起用された。
そのとき、強く違和感を覚えたという。
「何のために部内戦やってんだよ、って思いました」
感情的になりながらも、理由を求めて監督に話しに行った。結果として、出場の機会は与えられた。

振り返ると、勝ちたかったというより、「納得できない状態のまま終わりたくなかった」のだと思う、と彼は話す。
この感覚は、今の仕事にもどこかで残っている。筋を通すことは、声を上げることでもあった。
「人より倍やれ」と言われて育った
彼の中には、昔から残っている感覚がある。「勉強ができない」という自己認識だった。
親族には国立大学出身者が多く、自分だけが劣等生なのではないか、という意識があったという。
周囲からは「頭が良さそう」と見られることもあったが、内側の感覚は違っていた。
家庭でよく言われていたのは、こんな言葉だった。
「できないなら、人より倍やれ」
彼は、その言葉を美化もしないし、否定もしない。
才能があるかどうかより、まず量を重ねる。
向いているかどうかより、続ける。
ただ、その前提にあった感情については、こう振り返る。
「正直、つらかったですね。才能ないなって思ってました」
それでも、動くしかなかった。
考えて立ち止まるより、手を動かすことでしか前に進めなかった。
新人時代の踏ん張り方にも、この感覚はつながっている。
新人時代、「結果につながった」ことで手触りが変わった
知識があっても、どう使えばいいのかは分からなかった。
学生時代、解剖学や運動学を学んではいたが、それが目の前の人の身体とどう結びつくのか、実感は持てていなかった。
新人として現場に立ってからも、その感覚はすぐには変わらなかった。勉強しているつもりでも、「これで合っているのか」という迷いが残っていたという。
それでも、先輩に勧められて勉強会に通い始めた。岡山や鹿児島まで足を運び、学んだことをそのまま真似するのではなく、「この人の場合はどうだろう」と考えながら現場で試すようになった。
すると、あるとき患者の反応が明確に変わった。
「楽になったよ」
「動かしやすくなりました」
そう言われた瞬間、これまでの学びや経験がつながった。
「確証を持ってできた、って感覚が初めてあったんですよね」
それまでは、なんとなく良くなっている気がする、という手応えだった。このとき初めて、「自分の判断が結果につながった」と言える感覚を持てた。
勉強は、やらされるものではなくなり、”自分の仕事を前に進めるための道具”として、意味を持ちはじめた。
子どもが生まれて、“やめる”決断をした
結婚と転職を経て、彼は整形外科の現場で働くようになる。
もっと学びたい、成長したいという気持ちは強かった。
一方で、夜遅くまでの勤務が続き、家庭とのバランスは崩れていく。
「子どもが、俺にあんまり懐かなくなってきて」
四ヶ月ほど経った頃、「このままじゃだめだ」と感じ、その職場を離れる決断をした。
「子育てと両立しながらやっていかないと、誰も幸せにならないな、って思った」
続けるために、いったんやめる。この判断は、働き方を見直すきっかけになった。
アウトプットが、次の環境を連れてきた
「学んだことは、外に出さなければ身につかない」
そう言われて、彼は学会発表にも挑戦するようになった。
得意だったわけではない。むしろ、人前で話すことは苦手だった。
初めての大きな発表は福岡。200人ほどの専門家を前に、一人で登壇した。
「震えてました。終わった後、何話したか覚えてないです」

それでも、発表をやめようとは思わなかった。毎年一度はアウトプットする、と自分の中で決めた。
質問を受けることで、自分の理解が曖昧な部分が見える。それを埋めるために、また学ぶ。
その積み重ねの中で、膝の分野を専門とする理学療法士とつながり、毎月研修に通う環境が自然とできていった。
正解を教えてもらうというより、答え合わせができる場所に身を置いた感覚だった。
アウトプットは、環境を変える行為でもあった。
「もう少し早い段階で」関われたら
老人ホームや病院での経験を通じて、彼が口にするようになった言葉がある。
「もう少し早い段階でやれてたら」
手術が悪いわけではない。
必要なときに、必要な治療として選ばれる手術もある。
ただ、多くの人が「できれば手術はしたくない」と思っているのも事実だ。
実際、現場で関わる人の多くは、すでに状態が進んでいるケースだった。
痛みが強くなり、日常生活に支障が出てから、ようやく相談につながる。
その段階では、選択肢が限られてしまうことも少なくない。
一方で、もっと早い段階――
違和感が出始めた頃や、少し動きにくいと感じ始めた頃であれば、手術をせずに済んだり、日常生活がぐっと楽になるケースも確かにあった。
だからこそ、悪くなる前の段階で関わること。
劇的に治すことよりも、
「これ以上悪くならないよう整える」
「回復できる余地を残す」
そんな関わり方に、自然と関心が向いていった。
その延長線上にあったのが、YouTubeだった。
治療が必要になる前の人たちに、もう一歩手前で声をかけられないかと思った。
再生数や登録者数を増やすことが目的だったわけではない。
動画の内容も、強い変化を約束するものではなく、「これ以上悪くならないためにできること」を淡々と伝えるものが中心だった。
画面の向こうには、まだ病院に行くほどではないと感じている人や、違和感を抱えたまま様子を見ている人がいるかもしれない。
そうした人たちを思い浮かべながら、彼はこう話す。
「治せなくても、立ち止まるきっかけにはなれるかなって」
できることは限られている。それでも、関われる位置を少し前にずらすことはできる。
迷いの中で、残したいものがある
将来について聞くと、彼は少し間を置いてから、こう答えた。
「今、迷ってるところですね」
はっきりとした計画があるわけではない。
何年後にこうなりたい、という輪郭もまだ描けていない。それでも、考え続けていることはある。
その一つとして出てきたのが、「ひざ痛」に関する書籍を出したいという話だった。
「形になるものを残していきたい」
理学療法士として何かを成し遂げた、という実感があるわけではない。
それでも、現場で見てきたことは確かにある。
「もう少し早い段階で関われていたら」と感じる場面。
悪くなってからではなく、悪くなる前に手を差し伸べられたかもしれない人たち。
その積み重ねを、整理して残したいと思った。
答えを提示するためではなく、「こういう考え方もある」と並べておくために。

──
ここで語られているのは、成功の話ではない。
「ない」ものを努力で埋めてきた物語でもない。
むしろ、自信があるわけでも、確信があるわけでもないまま、それでも進める形を探し続けてきた過程が、そのまま置かれている。
彼は今も、答えの出ない問いに向き合いながら、現場に立ち続けている。
山岸さんより
もし、この記事を読みながら、少しだけ立ち止まる感じが残ったなら、そのままにしておいてもいいと思います。
はっきりした答えがなくても、迷っている時間ごと、誰かの言葉に触れることはできるので。
編集後記(インタビュアーより)
話を聞いているあいだ、山岸さんは、自分の選択を大きな出来事として語ろうとしなかった。
振り返ると、節目というより、立ち止まったまま考えていた時間が多く残っている。
すぐに答えが出る話ではなく、「まだ分からない」という状態を、そのまま言葉にしていく取材だった。
言葉の間にあった沈黙や、考えながら話す時間が、記事の中にも滲んでいる気がする。
何かを証明するための時間ではなく、今いる場所を確かめながら、次に進む位置を探している時間だった。




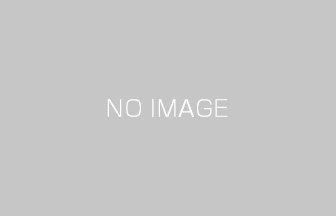




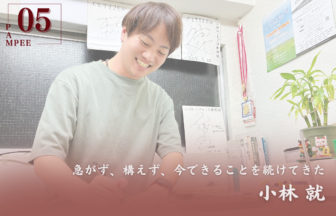
この記事へのコメントはありません。