── いくつもの選択を重ねながら進んできた、田端 駿さんの実例から
答えが出ず、不確かさを抱えたまま進んでいる人。
立ち止まるたびに不安や迷いが出る人。
そんな人に向けて。
この記事は、選び直しや立ち止まりを含んだ時間を、そのまま書き出した記録である。
プロフィール
名前:田端 駿(たばた・しゅん)
活動エリア:関東
肩書き:不用品買取営業/主任
主な仕事・活動内容
商業施設などの催事現場を中心に、不用品買取の営業を行う。個人プレイヤーとして成果を上げながら、主任としてチームマネジメントも担っている。
これまでの経歴・経験
高校まで野球に打ち込み、大学進学後は競技から離れる。大学時代はボランティア、海外渡航、インターン、発信活動など複数の選択を経験。転職を経て現在の会社に入社し、半年ほどで主任に昇格。
「濃すぎた一年」を振り返る
彼は、事前アンケートを書いたときのことを思い出しながら、この一年を振り返っていた。
「1年が濃すぎて。人生の中で、あの部分だけで相当濃かったなって実感しました」

不用品買取の営業として現場に立ち続け、数字と向き合い、結果を求められる日々。
その中で、自分の性格や、これまでのやり方が、はっきりと浮かび上がってきた感覚もあったという。
高校野球以来、何かひとつに集中して取り組んだ時間だったとも語る。
「うまくいった成功体験を振り返ると、やっぱり一つに対して集中してやってたなって思います」
この一年は、その性質が、結果や関わり方に、そのまま表れていた時間だった。
プレイヤーから、背負う側へ
主任になり、成果を出す役割から、成果を支える役割に変わった。
その変化は、昇格した瞬間に実感できたものではなかった。
数字を出すこと自体は、これまで通り続いていた。
ただ、チームを任されてから、同じ行動をしても、返ってくる反応が変わった。
自分なら自然にやること。
先輩の音声を聞くこと。
フィードバックを求めること。
それらは、メンバーにとっては「負荷」になることもあった。
「自分の当たり前が、当たり前じゃないんだなって」
ボイスレコーダーを使った振り返りも、その一つだった。
目的は、営業力を上げること。
だが、送られてくる音声は、必ずしも意図したものではなかった。
内容を聞きながら、どこに声をかけるべきか迷う場面も増えた。
「手段、失敗したなって思いました」
言葉は変わってきている。
行動も、少しずつ変わり始めている。
それでも、上から求められる水準と、現場の現実のあいだに立つと、判断が止まる。
主任としての役割と、現場で動いてきた自分。
「主任の自分と、田端駿の自分の間で葛藤してますね」
悔しさが残っている場所
高校時代の話になると、声の調子が少し変わった。
思い出そうとしても、すぐには浮かばない時間が多い。
野球以外の生活について聞くと、「覚えていない」という言葉が、何度か繰り返された。
「家での記憶が、あんまりないんです」
家庭の環境が変わっていた時期でもあった。
ただ、そのことを当時どう感じていたかは、はっきりとは思い出せないという。
楽しかったかと聞かれると、答えは即座だった。
「楽しいこと、なかったと思う」
それでも、強く残っている場面がある。
高校三年の夏、最後の大会だった。

「三年間やって、最後にメンバー落ちして終わった」
中学までは、役割も結果もあった。
高校では、同じやり方が通用しなかった。
声を出し、雰囲気をつくる役に回ったが、それが結果につながることはなかった。
「頑張る方向、ずれてたなって今は思います」
当時は、そのズレを言葉にできなかった。
ただ、時間だけが過ぎていった感覚が残っている。
野球を降りた瞬間の判断
メンバー落ちをきっかけに、野球を続ける選択肢は消えた。
感情が整理されるよりも先に、判断が決まっていた。
「野球じゃ勝てないなって思いました」
続ける理由を探すより、「ここではない」という感覚の方が強かった。
違うレールに行く。
そう決めたものの、その先で何を目指すかは、まだ定まっていなかった。
大学進学も、明確な目的があったわけではない。
学部も、「探す時間」として選んだ。

ダイビング、海外、ひとり旅。
人と違うことを選びながら、自分の立ち位置を探していた。
その途中で、迷走する時期もあった。
就活支援やSNSのコミュニティに触れ、うまくいかなさも経験した。
「でも、それがあったから、今の自分があると思ってます」
ただ、そのときは「これだ」と言える感覚はなかった。
掴んだというより、探し続けている時間だった。
尖っていた頃の自分
大学後半、彼は「尖っていた」と周囲から言われる時期があった。
本人にとっては、特別に反抗していたつもりはなかったという。
ただ、自分なりに「正しい」と思う方向へ、そのまま進んでいただけだった。
「その時集中していたものに自信をもって、今の時代はこうだろ、って主張してました」
同年代と話していても、どこかで距離を取るような言い方になっていた自覚はある。
それは、小学生の頃の感覚に近かったとも話す。
前に立ち、声を出せば、自然と人がついてきた時代。
当時は、なぜ人がついてくるのかを考えなくても、うまく回っていた。
しかし、高校以降、その前提は少しずつ崩れていった。
同じように前に立っても、人は思ったようについてこない。
「感覚でできてたことって、再現性ないんだなって、後から思いました」
その違和感を、すぐに言葉にすることはできなかった。
「自分が変わったのか」
「周りが変わったのか」
はっきりしないまま、時間だけが過ぎていった。
ただ、“うまくいっていた頃のやり方”が、そのままでは通用しないという感覚だけは、確かに残っていた。
そしてその感覚は、自分がどんな人と、どんな距離で関わるのかを、静かに選び直すきっかけにもなっていった。
「深さ」に惹かれる理由
彼が惹かれるのは、自分にない考え方を持つ人だという。

話していて、視点がずれる感覚。
「その視点なかったです、って思える人が好きです」
それは、単に知識が多いとか、経験が豊富という話ではない。
うまくいかなかった経験。
落ちた時間。
思うように進めなかった過去。
そうしたものを通ってきた人の言葉には、
感覚だけでは辿り着けない重さがあると感じている。
「下を知ってる人間の方が、深みが増すと思ってます」
かつて、感覚だけで前に立てていた自分。
その感覚が通用しなくなった時間。
その両方を経験したからこそ、彼は「正しさ」よりも、「どこを通ってきたか」を見るようになった。
誰かの言葉に触れながら、自分の考えも、少しずつ書き換えていく。
「深さ」に惹かれるという感覚は、誰かに答えを求めたい気持ちというよりも、もう一度、自分の立ち位置を確かめ続けるための姿勢に近いのかもしれない。
立ち止まりながら、選び直してきた
話を重ねるうちに、彼の時間は一直線ではなかったことが浮かび上がる。
高校野球での挫折。
野球を降りる判断。
大学での模索。
社会人になってからの選び直し。
「落ちてもいいし、止まってもいいと思ってます」

止まることも、選び直すことも、必ずしも前に進むための準備とは限らない。
そのときどきで、自分の足元を確かめていただけだった。
「ちゃんと向き合うって、楽しいなって思えるようになりました」
今も、何かが定まった状態ではない。
ただ、急がなくていいものと、無理に決めなくていいものが、少しずつ分かってきている。
本人から
変わりたいと思っている途中の人には、たぶん、近い話なんじゃないかなと思います。
自分も、何かが決まった状態でここにいるわけじゃないし、もう、できあがった人の話でもありません。
選び直したこともあるし、止まった時間も、正直ありました。
たぶん、今も途中なんだと思ってます。
誰かに強く届けたいというよりは、自分の経験を、そっと置いておく、そのくらいの感覚に近いです。
もしどこかで届いたら、そのときに、見てもらえたら。
それでいいかなと思ってます。
編集後記(インタビュアーより)
話を聞いているあいだ、何かを証明する時間ではないと感じていました。
過去を整理するというより、今の地点を確かめる作業に近かったと思います。
強さと迷いが、同じ文脈で語られていたのが印象的でした。
振り返ると、答えを出す場面はほとんどありませんでした。
ただ、言葉が置かれていく時間だったように思います。









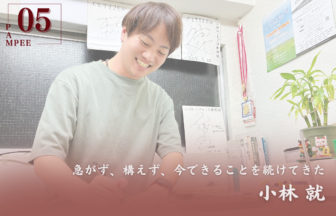
この記事へのコメントはありません。