── 料理人・片岡 愛起さんの実例から
今も、彼は料理の現場に立っている。
ただ、そこで起きていることは料理の話だけではない。
役割や場面が変わるたびに、言葉にしきれない感覚が残る。
この記事は、答えを示すものではなく、途中の記録だ。
プロフィール
名前:片岡 愛起(のりき)
活動エリア:関東圏を中心に各地
肩書き:料理人(フレンチシェフ)
主な仕事・活動内容
レストランで培った技術と現場力を土台に、現在は 出張料理/ケータリング/料理教室 を中心に活動。「ちゃんと美味しい」だけで終わらせず、場の空気ごと整う料理を目指している。
これまでの経歴・経験
「ひらまつ」系:広尾本店(3年半)大阪(約1年)→ 京都(約2年)ほかグループ内で経験
フランスでの修行経験。フランス料理歴13年。
熱海の高級ホテル「ATAMI せかいえ」勤務
泣き虫だった、という記憶
彼は、自分の幼少期を振り返るとき、
「泣き虫だった」という言葉を何度も使う。
小学校の頃、些細なことで泣いてしまい、
それがきっかけでいじられることが続いた。
本人の記憶では、「毎日泣いていた」感覚が残っている。
放課後になると、違う時間が始まった。
夜、ドッジボールの練習に向かう。
昼間とは別の場所へ、身体を運ぶ。
同じ年齢でも、関係性は違っていた。
先輩や後輩は、学校での彼を知らない。
そこでの立ち位置は、最初から決まっていなかった。
「学校生活の中では自信はなかったけど、ドッジボールの中では違った」
全日本大会に出場した経験もある。
しかし、学校に戻れば、扱われ方は変わらなかった。
それでも、夜の練習は続いた。
外に出ることで、すべてが変わるわけではなかったが、
同じではない時間が、確かに存在していた。
笑って流す、という選択
中学生になる頃、泣くことは減っていった。
代わりに、笑って流すようになった。
「笑っといた方がいいな、って思ってた」
怒られても、翌日には引きずらない。
「まあしょうがないよね」と切り替える癖は、
この頃についたものだと彼は話す。
ただ、扱われ方が変わったわけではなかった。
「笑って流せるようになったけど、変わらなかった」
見た目を変えれば何かが変わるかもしれない。
そう思って髪型を変えた時期もある。
けれど、周囲の反応は大きくは変わらなかった。
高校に進学し、地元から離れても、
グループの中での立ち位置は似ていた。
一対一では普通に話せる。
人前では、求められる役割こなす。
心に違和感は合ったが、
流す方が、現実的だった。
専門学校で、広がった輪
料理の専門学校に入ってから、環境は変わった。
入学前にSNSでつながっていた人たちがいた。
クラスの外にも知り合いがいる。
そのことが、場の見え方を変えた。
彼は授業にもきちんと向き合った。
強い競争心があったわけではない。
「競争心はないけど、できるようにはならないと」
放課後の勉強会にも参加して、
誰よりも料理と向き合った。
その積み重ねで、
クラス内での立ち位置は、少しずつ変わっていった。
料理人としての時間
19歳で料理の道に入った理由について、
彼は強い動機や理想像を語らない。
ただ、「やってみたら続いた」という感覚が近い。

現場に出てからは、長い労働時間が続いた。
朝から深夜まで、同じ作業を繰り返す日々だった。
彼は「しんどかった」とは言うが、
「辛かった」とは言わない。
「探究してる感じの方が強かった」
「しんどかったけど、辛くはなかった」
料理の工程は、身体に入っていった。
考えなくても、手が動くようになる。
レストランでは、料理が主役だった。
食べに来る人がいる場所だった。
評価は、料理の出来で決まる。
その前提に、疑問はなかった。
飛び出す前夜の感覚
会社を辞める決断は、突然ではなかった。
「辞めたい」という言葉は、早くから口にしていた。

実行までには、数年かかった。
迷いというより、
具体的な問題が一つずつ残っていた。
荷物の行き先。
住む場所。
次の仕事。
辞める前夜も、彼は平静を装っていた。
周囲に悟られないよう、
いつもと同じように振る舞っていた。
「いかに悟られないようにするかを考えてた」
仕事を終え、帰宅してからも、
気持ちが切り替わる感じはなかった。
部屋の中で、
少しずつ荷物をまとめる。
必要なものと、
今は持っていかないものを分ける。
大きな整理はしなかった。
目につくところだけを動かす。
忘れ物がないかを確かめる。
ドキドキはしていた。
それと同時に、
どこか落ち着いてもいた。
「なんとかなるだろう、って思ってた」
その夜は、
「決断した」という感覚よりも、
やるべき作業を一つずつ終えた、
という感覚に近かった。
翌朝、
店に退職届が届いたのは9時頃だった。
その時間から、
電話が何度も鳴り始めた。
彼は、出なかった。
「鬼びように電話かかってきたけど、無視してた」
LINEでも連絡が来た。
「このままでは手続きができないので、連絡してください」
それも、すぐには返さなかった。
数時間後、
一度だけ短く返した。
「弁護士にも確認しているので、
大丈夫だと思います。」
それ以降、
連絡は来なくなった。
立ち止まる選択はなかった。
考え続けるより、
動かない時間をつくらない方が、
その日を越えられた。
その夜と翌日は、
大きな区切りのようでいて、
彼にとっては、
淡々と過ぎていく時間だった。
見るようになったのは、人の動き
料理歴が重なるにつれ、
彼の中で料理は「考えずにできるもの」になっていった。

火加減、盛り付け、段取り。
意識しなくても、手が動く。
レストランでは、その精度を
高い水準で保つことが求められていた。
評価は料理の出来で決まる場所だった。
ただ、独立して扱う現場が変わるにつれ、
求められるものも変わっていった。
イベント、立食、年齢層の幅がある食事会。
そこでは、
世界一の一皿は必要とされていなかった。
「自分が作りたいものを作ることは、ほとんどない」
依頼があれば、まずヒアリングをする。
誰が来るのか。
どんな目的で集まっているのか。
この会で、どんな時間が流れてほしいのか。
ロングパスタにするか、
ショートパスタにするか。
トマトソースを避けるかどうか。
場の条件に合わせて形を変えていった。
料理を通して、
人がどう動くのかを見るようになった。
「料理は脇役」という言葉
独立してしばらく経った頃、
彼の中で一つの言葉が定着する。
「料理は脇役」
レストランでは、料理が主役だった。
料理を食べに来る場所だった。

けれど、今いる現場は違う。
人が集まり、話し、時間を共有する場だった。
「会のメインは、料理じゃない」
「コミュニケーションが一番大事」
彼が嬉しいと感じる瞬間も、
次第に変わっていった。
料理は、
その場を円滑に進めるための一要素になる。
「美味しいって言葉はいらない。なくなってるのが嬉しい」
言葉より、行動。
皿が早く空く。
おかわりが出る。
「美味しい」と言われることより、
その場で会話が生まれること。
人と人が自然につながっていくこと。
「料理があることで、会が楽しかった、になってたらいい」
料理が主役でなくなったことに、
強い違和感はなかった。
むしろ、
その方が自分にはしっくりきた。
そこで、
彼が大切にしている距離感が、
静かに残っている。
本人から
自分も、まだ途中だと思っています。
決まっている感じは、正直あんまりありません。
これで合っているのかどうかも、自分ではよく分からないまま、やっています。
料理がどうとかもそうですし、会がどう終わるかを、ただ見ているだけのときもあります。
もし届くなら、それでいいかなと思ってます。
編集後記
話を聞いているあいだ、
何度も「定まっていない」という感覚が残った。
答えを出すための時間ではなく、
今いる場所を確かめているような時間だった。
料理の話をしていても、
視線はいつも少し外側にあった。
何かを証明するより、
場に何が残るかを見ている人なのだと感じた。



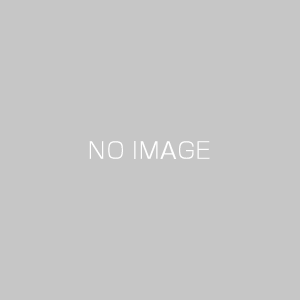





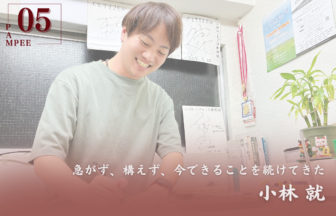
この記事へのコメントはありません。